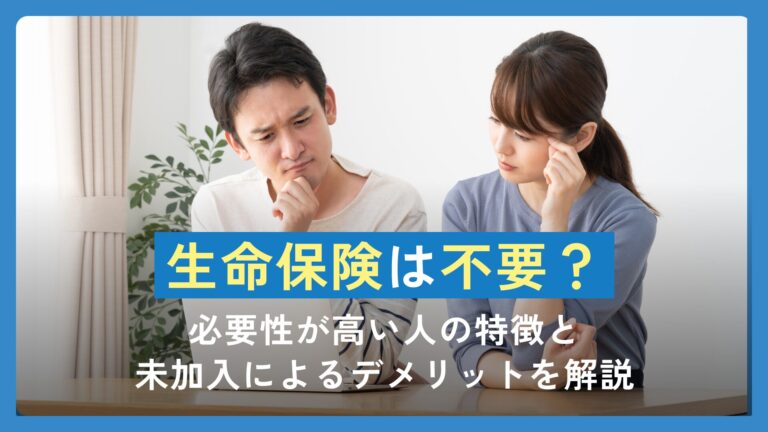「生命保険は必要ない」そんな声を一度は耳にしたことがあるかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか?
近年では社会保障制度の見直しや物価上昇もあり、公的な保障だけで将来のリスクすべてに備えるのは難しい状況になりつつあります。特に、家族を養っている方や貯蓄に不安のある方にとって、万が一の事態が発生した場合、その経済的インパクトは想像以上に大きなものです。
生命保険は、社会保障制度だけではカバーしきれない部分を補う「自助」の手段。国も民間保険の活用を推奨しており、今やライフプラン設計の基本とも言える存在です。
この記事では、生命保険の必要性が問われる背景や、「いらない」といわれる理由、加入しないことで生じるデメリット、そして本当に必要な人・そうでない人の特徴を解説します。生命保険の必要性について、あなた自身の状況と照らし合わせながら、今こそ冷静に考えてみませんか?
生命保険は本当に必要ないのか?

生命保険は「本当に必要ない」と言い切れるものなのでしょうか?その問いに答えるには、まず生命保険の仕組みや役割を正しく理解することが大切です。
生命保険は、多くの人が保険料を出し合い、万が一のときに経済的支援を受けられる「相互扶助」の考え方に基づいた仕組みです。主な保険の種類には、死亡保険、医療保険、がん保険、個人年金保険などがあります。死亡保険は、被保険者が亡くなったり、所定の高度障害になった場合に保険金が支払われ、残された家族の生活を支えます。医療保険やがん保険は、手術や入院といった高額な医療費への備えとなり、個人年金保険は老後資金を計画的に準備する手段です。
こうした保障機能を持つ生命保険は、単なる「不要論」で語れるものではありません。生命保険の必要性は、家族構成や経済状況、将来のリスクに対する備え方によって大きく異なるからです。
【関連記事】
生命保険に入らないと後悔する?失敗事例と加入すべき人の特徴を解説
日本人における生命保険の加入率

出典:2022(令和4)年度生活保障に関する調査 207ページ
日本では、多くの人が生命保険の必要性を認識し、実際に加入しています。
生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によれば、生命保険の加入率は男性77.6%、女性81.5%という高い水準を記録しており、なかでも50代が男性86.9%、女性87.8%と最も加入率の高い年代とされています。
このデータから、将来のリスクへの備えとして生命保険が広く活用されていること、そして多くの人が何らかの形で必要性を感じていることがわかります。
生命保険の役割
生命保険は、人生に潜むさまざまなリスクに備えるための経済的なセーフティーネットです。
近年では、物価の高騰による支出の増加や、生活費やローンの支払いなど家計の固定費が高くなっており、突然の入院や大黒柱の死亡などによって収支のバランスが一気に崩れるリスクが高まっています。独身者であっても、病気や事故によって働けなくなると生活が立ち行かなくなる可能性があります。
また、「長生きリスク」という言葉があるように、長生きすればするほど老後の生活費に対する不安は増し、必ずしも老後に十分な収入が得られるとは限りません。
このように、人生のあらゆる段階で私たちは経済的リスクと隣り合わせにあります。生命保険は、それらの不安を事前に和らげる手段として役立ちます。
つまり、生命保険の必要性とは「将来の不確実性を見越して、安心できる備えをつくること」に他なりません。
生命保険がいらないと言われている理由

生命保険の加入率は高い一方で、「生命保険は不要」との声も一定数存在します。
その背景には、公的制度の充実や、実際に保険を利用する場面の少なさ、そして個人での備えがあれば十分という考え方があるようです。
ここでは、生命保険の必要性が疑問視される代表的な3つの理由を取り上げ、それぞれの考え方を詳しく見ていきましょう。
1. 日本は国民皆保険制度を採用しているから
日本には全国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」があり、病気やケガをしても自己負担は原則3割で済みます。また、一定額を超える医療費については高額療養費制度が使えるため、実質的な負担を抑えることも可能です。
さらに、遺族年金制度があるため、万が一世帯主が亡くなっても、一定の生活保障が受けられる仕組みも整っています。こうした制度があることから、「民間の生命保険に頼らなくてもいいのでは」と考える人がいるのも自然です。
しかし、公的保険の対象外となる費用(差額ベッド代、先進医療費など)や、遺族年金を受け取れないケース(例:子どものいない個人事業主など)もあり、制度だけで完全に備えることは難しい場合もあります。老後の生活費についても、公的年金だけで十分とは言えないケースも多くあります。
このように、制度の仕組みを理解したうえで「生命保険の必要性」を判断することが重要です。
2. 実際に保険を使う場面が少ないから
「どうせ保険なんて使う機会がない」という意見も、生命保険に加入しない理由として多く見られます。
たしかに、厚生労働省のデータによれば、人口10万人あたりの入院者数は945人(入院率1%弱)、40歳男性の死亡率は1,000人中1人、女性は0.59人と、若年層では病気や死亡の確率が低いのが現実です。(参照:令和5年簡易生命表の概況|厚生労働省)
こうした統計だけを見ると、保険に加入する必要性を感じにくいのは当然かもしれません。
しかし、年齢を重ねるにつれて病気や入院のリスクは確実に高まります。健康な若いうちに備えることで、将来の保険料負担を抑えることもできます。生命保険の必要性を過小評価せず、将来のリスクに対して冷静に備える必要があります。
3. 貯金があれば対応できるから
「十分な貯金があるから、わざわざ保険に入る必要はない」と考える方もいます。
たしかに、生命保険は病気や死亡といった事態に備える仕組みであるため、それに対応できるだけの資金があれば、保険に加入する必要は低いと考えられる側面もあります。
しかし、想定外の大きな出費が重なった場合、貯蓄だけでは対応しきれない可能性もあります。特に、重病による長期入院や、高額な治療、働けない期間が続いたときなどは、収入の減少と支出の増加が同時に訪れます。
「備えはある」と思っていても、その備えが現実に足りるかどうかを検証したうえで、生命保険の必要性を再評価することが大切です。
生命保険に入らないことで起こりうるデメリット

生命保険に未加入の場合、万が一の際に家族が経済的に困窮する可能性が高まります。また、医療費の自己負担が増加し、老後の生活資金が不足するリスクもあります。
ここからは、生命保険に入らないことで起こりうるデメリットを具体的に見ていきましょう。
万が一の時に金銭的な問題で家族が困る
一家の働き手が突然亡くなる、または重い障害を負った場合、残された家族は生活資金の確保という現実に直面します。特に貯蓄が十分でない家庭では、公的な支援に頼らざるを得ないケースも多く、生命保険の必要性が高まります。
家族を支える人が亡くなった場合、国の制度として「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」が用意されています。これらは家族構成や故人の年金加入状況により、支給の有無や金額が異なります。
| 年金の種類 | 受給対象者 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方) のある配偶者 または 子 |
| 遺族厚生年金 | 死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方 1. 子のある配偶者 2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または23級の状態にある方。) 3. 子のない配偶者 4. 父母 5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。) 6. 祖父母 |
遺族基礎年金の受給額は、子どものいる配偶者が受け取るときには「「831,700円+子の加算額」、子どもが受け取るときには「831,700円+2人目以降の加算額」で計算されます。(昭和31年4月2日以後生まれの配偶者の場合)
子どもの加算額は、1人目および2人目が各239,300円、2人目以降が各79,800円となっています。(※参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構)
| 子どもの人数 | 遺族基礎年金額(年額) |
|---|---|
| 1人 | 1,071,000円 |
| 2人 | 1,310,300円 |
| 3人 | 1,390,100円 |
遺族厚生年金は、被保険者の収入や加入期間に応じて、配偶者や子ども、場合によっては親族へ支払われる制度です。年金額は故人の厚生年金報酬比例部分の4分の3とされ、受け取る金額は生前の給与や加入月数によって変動します。
しかし、これらの制度だけで遺族の生活がすべてまかなえるとは限りません。公的保障の仕組みを理解したうえで、不足する部分をどのように補うかを考えることが、生命保険の必要性を判断する鍵となります。(参照:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構)
入院・治療時に自己負担が大きくなる
ケガや病気で療養した場合、患者は医療費の1~3割を自己負担します。大きな手術や長期入院をすると、医療費が高額になり、自己負担額も増加します。また、公的医療保険の対象外となる費用(差額ベッド代、先進医療費、入院中の食事代、自由診療など)は「高額療養費制度」の対象外となり、全額自己負担となります。
さらに、健康状態によっては保険に加入できなくなってしまう場合もあります。「引受基準緩和型」の医療保険もありますが、一般的な医療保険よりも保険料が高く、付加できる特約が少ない、一定期間給付額が制限されるなどのデメリットがあります。
老後の生活が困窮する可能性がある
「長生きリスク」という言葉があるように、老後は十分な収入が得られず、長生きすればするほど老後の生活費に不安が生まれる状況も考えられます。公的年金や貯蓄で老後の生活費をまかなう場合、老後資金が不足する可能性があります。自分や家族に介護が必要になると、生活費とは別に介護資金も用意しなければなりません。
生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によると、夫婦2人で老後生活を送る際の最低日常生活費は月額平均23万2,000円、ゆとりある老後生活を送るためには月額平均37万9,000円が必要とされています。
一方で公的年金の受給額の平均は以下のように推移しています。
| 年度 | 老齢厚生年金平均月額 |
|---|---|
| 令和3年度 | 145,665円 |
| 令和4年度 | 144,982円 |
| 令和5年度 | 147,360円 |
参照:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省
また、65歳以上の単身無職世帯の家計をみると、可処分所得約12.1万円に対して消費支出は約14.9万円で、約2.8万円が不足しています。(参照:家計調査 2024(令和6)年平均|総務省)
このように、老後の生活費が不足する可能性があるため、生命保険の必要性を検討する際は、十分な資産形成ができているかを慎重に考えることが必要です。
生命保険に加入することで得られるメリット

生命保険はいらないという意見もありますが、実際には多くの人にとって重要な備えとなります。
ここでは、生命保険に加入することで得られる主なメリットについて整理し、生命保険の必要性をあらためて見直すきっかけとしましょう。
万が一の場合に備えられる
生命保険の最大の魅力は、月々の保険料を支払うことで、もしもの事態に経済的な備えができるという点です。
たとえば、ケガや病気で入院・手術が必要になった際には、医療保険やがん保険から給付金を受け取ることができ、治療費の負担を軽減できます。また、特約を追加することで、さらに手厚い保障を得ることも可能です。主な特約には以下のようなものがあります。
- 通院特約:入院後の通院治療にも対応
- がん診断給付金:がんと診断されるとまとまった一時金を受け取れる
- 先進医療特約:健康保険の適用外となる先進医療の技術料をカバー
加えて、死亡保険に加入していれば、世帯の大黒柱に万が一のことがあっても、遺族は生活費や葬儀費用をまかなうことができ、経済的な混乱を避けられます。最近では、病気やケガで長期間働けなくなった場合に収入減をカバーする「就業不能保険」の必要性も高まっています。
このように、死亡・医療・就労不能といった多様なリスクに対して、生命保険は幅広く備えることができます。
生命保険料控除で税金を抑えられる
生命保険に加入することには、税制面でのメリットもあります。
所得税・住民税の「生命保険料控除」を利用することで、年間の納税額を軽減することが可能です。たとえば、個人年金保険に加入していれば、将来の備えをしながら税負担を減らせるという、二重のメリットが得られます。
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険では、以下の3区分に分けて最大4万円(所得税)・2.8万円(住民税)の控除を受けられます:
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
具体的な控除額は以下の通りです。
| 年間払込保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 2万円以下 | 払込保険料の全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | (払込保険料 × 1/2)+ 1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | (払込保険料 × 1/4)+ 2万円 |
| 8万円超 | 一律 4万円 |
| 年間払込保険料 | 住民税の控除額 |
|---|---|
| 1万2,000円以下 | 払込保険料の全額 |
| 1万2,000円超〜3万2,000円以下 | (払込保険料 × 1/2)+ 6,000円 |
| 3万2,000円超〜5万6,000円以下 | (払込保険料 × 1/4)+ 1万4,000円 |
| 5万6,000円超 | 一律 2万8,000円 |
このように、保険は保障だけでなく節税にもつながるため、家計全体を見据えたうえでの活用が望まれます。
生命保険の必要性が高い人の特徴

生命保険の必要性はすべての人に等しいわけではなく、家庭状況や職業、貯蓄の有無などに応じて大きく異なります。
ここでは、特に生命保険への加入を検討すべきとされる5つのケースを紹介します。
家族を扶養している(特に子育て中)
家族を養っている人、特に小さな子どもがいる世帯では、生命保険の必要性は非常に高いといえます。
家計を支えている方が突然亡くなった場合、のこされた遺族の生活費を確保する必要があります。死亡保険などで備えておけば、遺族の生活費や教育資金に充てることができ、生活の安定を支える手段となります。
さらに、死亡時だけでなく病気・ケガへの備えも重要です。医療保険やがん保険で治療費をカバーできるほか、長期の休職による収入減には「就業不能保険」が効果的です。このように、生命保険は家族の暮らしを支える「経済的な土台」として大きな役割を果たします。
自営業やフリーランスで社会保障が薄い
自営業やフリーランスとして働く人は、会社員に比べて公的な保障が限定的であるため、生命保険の活用が非常に重要です。
たとえば、厚生年金ではなく国民年金にしか加入できないため、老後の年金額が少なく、万が一の遺族年金も低くなります。加えて、病気やケガで仕事を休んでも、会社員にある「傷病手当金」や「出産手当金」などの制度は利用できません。
こうした不足をカバーするには、死亡保険や医療保険、所得補償保険などを上手に活用し、自助努力でリスクに備える必要があります。公的制度の差を補完する意味でも、生命保険は自営業者やフリーランスにとって不可欠なセーフティーネットといえるでしょう。
貯蓄が十分でない
手元資金が少ない人ほど、生命保険の必要性は高まります。
病気やケガでの急な出費や、働けなくなった場合の収入減少は、生活に大きな打撃を与えるからです。たとえ高額療養費制度があっても、差額ベッド代や先進医療など、保険適用外の費用は自己負担となり、まとまった貯蓄がないと対応できない可能性があります。
このような状況を回避するには、医療保険や就業不能保険で支出や収入減に備えることが有効です。さらに、貯蓄性のある保険を選べば、将来の資産形成とリスク対策の両立も可能です。
老後資金に備えておきたい
将来に向けて計画的に資金を準備したい人にとって、生命保険は有効な選択肢です。
貯蓄性のある生命保険に加入すれば、保障が不要になった時点で解約返戻金を受け取ることができ、老後資金として活用できます。特に「個人年金保険」では、定年退職後の収入源として年金形式での給付が受けられるため、公的年金を補完する手段として活用されています。
日々の生活費からの積立が難しいという方でも、自動的に貯蓄できる生命保険を活用すれば、老後への不安を軽減できるでしょう。
【関連記事】
積立型生命保険とは?意味ない?メリット・デメリットや選び方を解説
相続税の対策をしたい
相続が発生した際、生命保険には「相続税の非課税枠」というメリットがあります。
具体的には、「500万円 × 法定相続人の数」までの保険金は非課税となるため、一定額までは相続税の課税対象から除外されます。さらに、保険金は原則として「受取人固有の財産」として取り扱われるため、スムーズに資金を渡せるのも特徴です。
ただし、受取人の保険金額が極端に偏る場合、特別受益とみなされて相続財産に持ち戻されるケースもあるため、事前の設計と家族間の話し合いが重要です。相続税対策としての生命保険の活用は、節税と円滑な資産承継の両方に役立ちます。
生命保険の必要性が低い人の特徴

生命保険はすべての人にとって絶対に必要なものではありません。ライフスタイルや資産状況によっては、加入しなくても十分に備えられるケースもあります。
ここでは「生命保険の必要性」が比較的低いとされる代表的な2つのタイプを紹介します。
独身・扶養家族がいない場合
扶養する家族がいない独身者にとっては、生命保険の必要性は低くなる傾向があります。
死亡時にのこされた家族を支える必要がないため、死亡保険の優先度は下がります。自分自身の葬儀費用や入院・治療に備えて一定の貯蓄があれば、多くの場合は十分に対応できるからです。
ただし、独身であっても病気やケガによって長期間働けなくなる可能性もあるため、就業不能保険や医療保険を検討する余地はあります。また、若いうちに加入すれば保険料が安く済むというメリットもあるため、将来のライフプランによっては早めの加入が有利になることもあります。
預貯金や資産が十分にある場合
十分な預貯金や金融資産がある人は、万が一の事態が起きても経済的に困る可能性が低く、生命保険での備えが不要なケースもあります。
たとえば、入院や手術などで医療費が発生した場合でも、自己資金で賄える余裕があれば医療保険の必要性は下がります。また、死亡時の葬儀費用や相続時の納税資金についても、手持ちの資産で対応できるのであれば、死亡保険の加入も必須ではありません。
ただし、資産がある人でも、相続対策や流動性確保の観点から生命保険を活用するケースはあります。状況に応じた見直しは重要です。
【関連記事】
生命保険の見直しとは?ベストなタイミングと見直し手順や注意点を解説
生命保険の必要性におけるまとめ

生命保険は「必要ない」といわれることもありますが、実際には日本人の多くが加入しており、その必要性は決して一概には語れません。人生には予測できないリスクが伴い、ライフステージの変化とともに必要な保障も変わっていくため、自分にとっての「生命保険の必要性」を見極めることが大切です。
生命保険は、万が一の事態に備えるための重要な備えです。扶養家族がいる人はもちろん、貯蓄が不十分な方や、社会保障の薄い自営業・フリーランスの方にも、一定の備えがあることで安心感を得られます。一方で、独身で十分な資産がある方などは、保険に加入しない選択も現実的です。重要なのは、自分のライフステージ・収支状況・将来の見通しなどを総合的に見て「自分に合った保障」を設計することです。
もし、自分に合う保険選びに不安がある場合は、保険診断サービス「ほけチョイス」の活用をおすすめします。スマートフォンやタブレットから簡単な質問に答えるだけで、自分に適した保険を診断できるだけでなく、営業担当による補足説明や見積書の作成なども受けられます。数多くの保険商品の中から納得のいく選択をするためのサポートツールとして活用してみましょう。
生命保険の必要性は人それぞれ。ライフステージの変化を見据えて、自分に必要な保障を見直し、安心できる未来に向けて備えておくことが重要です。