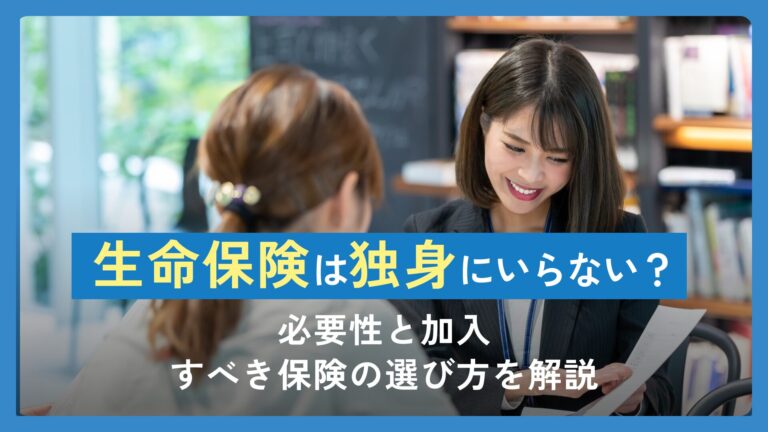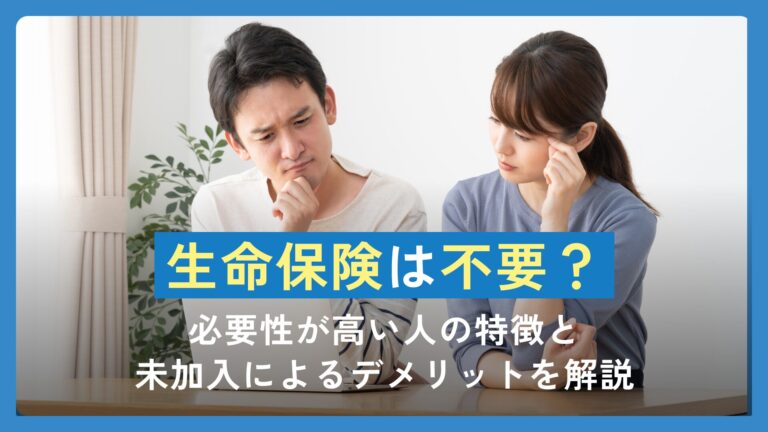「独身には生命保険はいらない」と思っていませんか?たしかに扶養家族がいない場合、死亡保障は必要ないと考える人も多いでしょう。
しかし実際には、病気やケガで入院したときの治療費や、働けなくなった際の収入減など、独身だからこそ自分ひとりでカバーしなければならないリスクが潜んでいます。
医療保険や就業不能保険など、必要な保障を見極めることで、将来の不安を大きく軽減できます。
この記事では、「自分には生命保険が本当にいらないのか?」を見直しながら、独身の方がライフスタイルや価値観に合った保険を選ぶための考え方と、おすすめの保険タイプをわかりやすく解説します。
独身者は生命保険の加入はいらない?

独身であることを理由に生命保険はいらないと考える方は少なくありませんが、実際には必要かどうかは一概には言えません。現在の貯蓄状況や生活スタイル、今後のライフプランによって、備えておくべき保障内容は大きく異なります。
たとえば、扶養家族がいないため死亡保障が不要なケースもあれば、将来の結婚や親の扶養、医療費の自己負担に備える必要がある場合もあります。
ここでは、独身者が抱える特有のリスクや、生命保険が不要とされる理由、そして加入が必要なケースについて、わかりやすく整理して解説します。
【関連記事】
生命保険とは?4つの種類から仕組みや必要性についてわかりやすく解説
生命保険は不要?必要性が高い人の特徴と未加入によるデメリットを解説
生命保険の加入はいらないと言われる理由
独身の人に生命保険がいらないと言われる主な理由は、扶養家族がいないことです。死亡保障は本来、遺された家族の生活費や教育費を補うことが目的であり、独身の場合にはそうした支出が発生しにくいため、保障の必要性が低いとされます。
また、公的医療保険制度が整備されている日本では、医療費の大部分を1〜3割の自己負担で済ませられるため、入院や治療が必要になっても多くのケースで支出を抑えられる傾向があります。
ただし、公的保険だけではまかなえない費用も多く、差額ベッド代や食事代、先進医療費用などは自己負担となります。
さらに、独身者でも親や兄弟を扶養している、離婚後に子どもの養育義務があるなどの事情がある場合は、死亡保障が必要です。
また、将来的に家庭を持つ予定がある場合は、若いうちから終身保険に加入しておくと、保険料を抑えつつ一生涯の保障を確保できるためおすすめです。
独身者が抱えているリスク
独身者が直面しやすいリスクとしては、病気やケガで入院したときに看病してくれる人がいない、老後に介護してくれる家族がいない、そして働けなくなった場合に収入が途絶えるといった点が挙げられます。
たとえば、長期入院や在宅療養が必要になった場合、自分自身で住居費や治療費を賄う必要があります。公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、入院時の自己負担費用は平均で約19.8万円とされており、状況によってはさらに高額になることもあります。
こうしたリスクに備えるには、医療保険や就業不能保険など、自分自身を守る保険を早めに検討することが重要です。年齢を重ねると保険料が上がり、健康状態によっては加入できなくなるリスクもあるため、早期の備えがおすすめです。
生命保険の必要性が低いと想定される方
独身でも生命保険の必要性が低いと想定されるのは、次のような条件を満たす場合です。
- 働けなくなっても生活には困らないだけの十分な貯蓄がある
- 万が一亡くなった時に備えて葬儀費用、身辺整理費用等、十分な準備ができている
なお、一般的な葬儀費用の目安は110万円~120万円程度とされています。これらの備えが整っていれば、新たに保険に加入しなくてもリスクに対応できる可能性が高いため、保険料の支払い負担を減らしたい方にとっては選択肢のひとつとなります。
独身者の生命保険加入率

独身の方は「生命保険はいらない」と考えがちですが、実際の加入率を見ると年代によって大きな差があることがわかります。
生命保険は家族を持つ人だけのものではなく、独身者にとっても医療費や老後資金などを備える手段として選ばれていることが数字から読み取れます。
ここでは、独身者の生命保険加入率の傾向と、年齢による違いについて詳しく解説します。
生命保険の加入率

生命保険文化センターの「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、個人年金を含む生命保険の加入率は、2人以上世帯で89.2%、単身世帯で45.6%と、独身の方の生命保険加入率は既婚者に比べて一貫して低く推移しています。
死亡保障は遺族の生活費を補うことを目的とするため、扶養家族のいない独身者にとっては必要性が低いと見なされがちです。
ただし、生命保険は死亡保障だけではなく、医療保険や就業不能保険、老後に備える個人年金保険といった多様な商品があり、目的に応じて選ぶことで独身者にとっても重要な備えとなり得ます。
保険に加入する目的を明確にし、必要最小限の保障を検討することで、コストを抑えながら安心を手に入れることが可能です。
年齢別の生命保険加入率

年齢が上がるにつれて、生命保険への加入率は上昇する傾向があります。生命保険文化センターの同調査によると、20代以下の加入率は27.8%と比較的低めで、30代前半は35.9%、30代後半では34.1%とわずかに減少しています。
しかし40代に入ると加入率は再び上昇し、40代後半では49.5%、50代前半は47.4%、50代後半に入ると50%を超え、70代後半では59.0%に達します。
この傾向からは、年齢を重ねるごとに健康リスクや老後の生活への不安が高まり、それに備える目的で保険への関心が高まっていることが読み取れます。
独身であっても年齢が上がるにつれて保障の必要性を感じ、加入する人が増えていることからも、生命保険が「いらない」とは一概に言い切れないことがわかります。
独身者におすすめな4つの生命保険

独身の方は「生命保険はいらない」と考えがちですが、実は備えておくべきリスクは意外と多く存在します。
特に、病気やケガ、就業不能、老後の資金不足などに対しては、家族の支援を受けにくい独身者だからこそ、適切な保障の準備が重要です。
ここでは、独身者にとって優先度の高い4つの生命保険を、リスク別にわかりやすく解説します。
1. 医療保険:入院や手術への備えに
医療保険は、病気やケガによる入院・手術・通院にかかる費用を保障する保険で、独身者にとって最も基本的かつ重要な備えです。看病してくれる家族が近くにいない場合でも、金銭的な安心を得られるため、自立した生活を送るうえで強い味方となります。
主契約の内容としては、入院給付金(入院日数に応じて給付金が支払われる)と手術給付金(手術の種類に応じた倍率で支払われる)の2つが主流です。
最近では、入院初日にまとまった金額を受け取れるタイプや、外来手術も保障対象とするタイプも増えており、保障の幅が広がっています。
さらに、三大疾病(がん・心疾患・脳卒中)や先進医療に備える特約を追加することで、高額治療への対応も可能です。これにより、独身者がひとりでも安心して医療に向き合える環境が整います。
【関連記事】
生命保険と医療保険はどう違う?種類やどっちに入るべきかを徹底解説
2. 就業不能保険:働けなくなったときの収入保障
就業不能保険は、病気やケガで長期間働けなくなったときに、保険金が支払われる保険です。一時金や毎月お給料のように年金形式で受け取るタイプがあります。
独身の場合、生活費を補ってくれる家族がいないため、収入が途絶えるリスクは特に深刻です。医師の指示による在宅療養や通院などで就業が困難な場合でも、家賃や生活費、光熱費などの固定費をカバーできるのが大きな特長です。
ただし、就業不能保険は、所定の条件(例:働けない状態が60日以上続くなど)を満たした後に支払われる仕組みで、免責期間が設定されています。免責期間が短いほど保険料は高くなります。
また、うつ病など精神疾患に対しては、保障の制限がある場合もあるため、加入前に給付条件をしっかり確認することが大切です。
独身で頼れる収入源が自分だけの場合、早めの備えが安心につながります。
3. がん保険:がん治療に備える保険
がん保険は、がんと診断された際や所定の治療を受けたときに、給付金が支払われる保険です。
がんは誰にでも起こり得る病気であり、独身者にとっては通院・入院・治療のすべてを一人でこなさなければならないケースが多くなります。特に、40代以降の女性や50代以降の男性では罹患率が大きく上昇するとされており、早期からの備えが重要です。
がん保険では、初回診断時の一時金のほか、長期の通院治療や再発時にも複数回給付金が支払われるタイプが増えています。また、入院を伴わない先進医療や外来での治療にも対応している保険もあり、実際の治療実態に即した保障設計が可能です。
なお、契約後一定期間(通常90日)の免責期間中は保障の対象外となる点にも注意が必要です。将来の医療リスクに備えておきたい独身の方にとって、がん保険は非常に実用的な選択肢といえます
4. 終身保険:一生涯の死亡保障
終身保険は、契約者が亡くなったときに必ず保険金が支払われる生命保険で、葬儀費用や死後の整理資金を確保する手段として有効です。
独身者でも、自分の葬儀代や身辺整理に関する費用を事前に準備しておきたいと考える方にとっては安心材料となります。
また、終身保険には一定期間以降に解約すると解約返戻金が受け取れるタイプも多く、老後の資金としても活用できる点が魅力です。
たとえば、低解約返戻金型終身保険は、契約初期の返戻率を抑えることで保険料を抑えられ、一定期間を過ぎると貯蓄性が高まります。また、外貨建ての終身保険は、為替リスクがある一方で、高い返戻率を期待できるというメリットもあります。
死亡保障と資産形成を兼ね備えた終身保険は、独身者にとって必要最小限の安心を手に入れる手段のひとつです。
【関連記事】
積立型生命保険とは?意味ない?メリット・デメリットや選び方を解説
年代別で独身者が加入すべき保険の選び方

独身の方にとっても、年代によって適した生命保険の選び方は異なります。年齢とともに病気のリスクや収入状況、貯蓄額などが変化するため、それに応じた保障内容の見直しが重要です。
特に、貯蓄額を判断する際には平均値よりも中央値を参考にするのが実態に近いとされています。中央値は全体の真ん中に位置する数値であり、極端に高額なデータに影響されないため、より現実的な基準となります。
こうした情報を踏まえながら、それぞれの年代で必要とされる保険の特徴を見ていきましょう。
20代〜30代の独身者
若い世代では「生命保険はいらない」と考える人も多いかもしれませんが、20代〜30代の独身者にとっても最低限の保障は備えておきたいところです。実際、病気やケガはいつ起こるかわからず、医療費や収入減に備えることは将来的な安心にもつながります。
医療保険は短期入院や手術などをカバーでき、保険料も若いうちであれば比較的安く抑えられます。また、就業不能保険も、万が一働けなくなったときに家賃や生活費を支える手段として役立ちます。
金融広報中央委員会の調査によると、20代単身世帯の金融資産保有額の中央値は103万円、30代は300万円とされており、長期の入院や治療にはやや不安が残る水準です。
終身保険を検討する場合は、保険料が安い若いうちに契約しておくことで、老後に備える長期的な保障を確保することもできます。独身のうちに保障の土台を築いておくことは、将来の不確実性に対する有効な対策です。
【関連記事】
30代におすすめの生命保険とは?選び方や保険料の相場・備えるべきリスクを紹介
40代以降の独身者
40代を超えると、病気やケガのリスクが一段と高まり、医療費や収入の減少に備えた保障の重要性が増します。また、金融広報中央委員会の同調査によると、40代の独身者の金融資産保有額の中央値は500万円、50代は555万円と言われており、すでに一定の貯蓄がある方も多い一方で、それだけでは不十分なケースもあります。
特に注意したいのは、がんの罹患リスクが急激に高まる点です。女性は40代から、男性は50代からがんの罹患率が上昇するため、がん保険や三大疾病特約などを活用して保障を手厚くしておくと安心です。
また、持病を抱えている場合や過去に大きな病気をした方でも加入できる医療保険の選択肢も増えています。女性であれば、乳がんや子宮系疾患などに特化した女性保険を検討するのもよいでしょう。
独身者にとっては自分自身が頼りです。年齢とともに変化するリスクに合わせて、保険内容を柔軟に見直すことが重要です。
【関連記事】
40代におすすめの生命保険は?ライフスタイル別に選び方を解説
50代におすすめの生命保険は?選ぶべき保険のタイプや見直し時の注意点を解説
男女別で独身者が検討すべき保険の選び方

独身の方が生命保険を選ぶときは、年齢だけでなく性別も重要な判断材料となります。なぜなら、病気のリスクや収入状況、ライフスタイルに男女差があるためです。
ここでは、独身男性と独身女性のそれぞれに適した保険の種類や選び方について解説します。
独身男性の場合
| 部位 | 生涯がん罹患リスク(%) | 何人に1人か | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
| 全がん | 63.3% | 50.8% | 2人 | 2人 |
| 食道 | 2.4% | 0.6% | 42人 | 175人 |
| 胃 | 8.9% | 4.3% | 11人 | 23人 |
| 結腸 | 6.3% | 5.8% | 16人 | 17人 |
| 直腸 | 3.7% | 2.3% | 27人 | 44人 |
| 大腸 | 10.0% | 8.1% | 10人 | 12人 |
| 肝臓 | 2.8% | 1.3% | 36人 | 75人 |
| 胆のう・胆管 | 1.4% | 1.2% | 70人 | 80人 |
| 膵臓 | 2.7% | 2.7% | 37人 | 36人 |
| 肺 | 9.7% | 4.9% | 10人 | 20人 |
| 乳房(女性) | – | 11.4% | – | 9人 |
| 子宮 | – | 3.6% | – | 28人 |
| 子宮頸部 | – | 1.3% | – | 77人 |
| 子宮体部 | – | 2.2% | – | 45人 |
| 卵巣 | – | 1.6% | – | 62人 |
| 前立腺 | 10.9% | – | 9人 | – |
| 甲状腺 | 0.6% | 1.6% | 180人 | 64人 |
| 悪性リンパ腫 | 2.3% | 2.0% | 43人 | 49人 |
| 白血病 | 1.1% | 0.8% | 93人 | 127人 |
参照:国立がん研究センターの「最新がん統計」累積がん罹患リスク(2021年データに基づく)
独身男性は比較的健康リスクが低く、特に若年層では保険がいらないと感じる方も多いかもしれません。しかし、国立がん研究センターの「最新がん統計」によると、日本人男性のがん罹患率は生涯で63.3%と高く、女性よりも12.5ポイント高い水準です。
がんにかかると入院や長期治療、場合によっては就業不能のリスクもあるため、若いうちからがん保険や三大疾病特約のある医療保険を検討しておくと安心です。
また、収入に余裕がある方は終身保険を通じて将来の備えを作るのも一つの選択肢です。保険料は若いほど割安で、長期的に見れば経済的負担も軽減できます。
独身女性の場合
独身女性は、男性に比べて平均年収が低く貯蓄額も少ない傾向があり、万が一に備えた経済的準備が課題となります。さらに、生命保険文化センターによると20代女性の10%が直近5年間で入院を経験しており、医療費の急な出費リスクも無視できません。
特に30代以降は乳がんや子宮筋腫など、女性特有の疾患のリスクが高まります。そのため、医療保険に加えて女性疾病特約の付いた保険や、女性保険を選ぶことで、通院・入院・手術にかかる費用をカバーしやすくなります。保険料の負担を抑えながらも、必要最低限の保障を確保することがポイントです。
男女それぞれで抱える健康リスクや経済状況は異なるため、独身だからといって生命保険がいらないと一概には言えません。自身の状況に合った保険を選ぶことで、将来の不安を軽減できます。
独身者が保険を選ぶときの注意点

生命保険は自分自身のリスクやライフスタイルに合わせて選ぶことが重要です。特に独身者は、自分の体調や収入状況をもとに、無理なく継続できる保障を見極める必要があります。
ここでは、独身の方が保険を選ぶ際に押さえておきたい3つの注意点を紹介します。
備えるべきリスクを把握する
独身者が保険を選ぶ際は、自分自身の生活スタイルにどんなリスクがあるのかを明確にすることが第一歩です。既婚者は家族への備えとして死亡保険を重視しますが、独身の場合は遺族を養う責任がないため、死亡保障の優先度は低くなります。
一方、自分自身が病気やケガで働けなくなるリスクや、長期の療養が必要になる状況にはしっかり備えておく必要があります。
医療保険や就業不能保険のように、自分の生活基盤を支える保障を中心に検討するのが現実的です。生命保険はいらないと一概には言えず、必要なリスクに絞って選ぶ姿勢が大切です。
ムリなく払える保険料にする
どんなに保障が充実していても、支払いが苦しい保険では継続が難しくなります。生命保険文化センターの調査による単身世帯年収別の年間支払保険料は以下の通りです。
| 年収 | 年間払込保険料 |
|---|---|
| 200万円未満 | 109,262円 |
| 200~300万円未満 | 122,588円 |
| 300~400万円未満 | 141,955円 |
| 400~500万円未満 | 170,188円 |
| 500~600万円未満 | 145,344円 |
| 600~700万円未満 | 189,527円 |
| 700~1,000万円未満 | 186,365円 |
| 1,000万円以上 | 306,381円 |
表を見てわかるように、収入に比例した負担が一般的です。生命保険がいらないと感じている独身の方も、まずは自身の収入に対して今の保険料が妥当かどうかを確認しましょう。
必要以上に高額な保険に入っている場合は見直しを検討し、保障と保険料のバランスを整えることが、家計を圧迫せずに安心を得るコツです。
保険に加入できなくなる場合がある
健康状態が良好なうちは「まだ保険はいらない」と思うかもしれませんが、それがずっと続くとは限りません。病気やケガが発覚してからでは、生命保険に加入できなかったり、給付条件が厳しくなったりすることがあります。
さらに、事故や転倒などによるケガは予測が難しく、救急搬送の約4人に1人が外傷によるものです。早めに保険を検討することで、健康なうちに備えを整えることができます。
独身者の生命保険に関するまとめ

独身だから生命保険はいらない、と考える人は少なくありません。確かに扶養家族がいないことや、公的保障制度が整っていることから、独身者の生命保険加入率は既婚者よりも低い傾向にあります。しかし、独身であることがリスクを完全に排除するわけではありません。
たとえば、病気やケガで長期間働けなくなった場合、独身者は自分の収入だけが頼りとなり、その収入が途絶えると生活に直結する影響が出てきます。
また、医療費や生活費の捻出もすべて自身でまかなわなければならず、貯蓄が十分でない場合は大きな負担となるでしょう。そのようなリスクに備えるためにも、医療保険や就業不能保険、がん保険といった保障を検討することは、決して無駄ではありません。
生命保険は「家族がいる人のもの」と決めつけるのではなく、自分のライフスタイルやリスクに合った内容を選ぶことが重要です。
万が一に備える生命保険を見直したい方は、スマートフォンやタブレットから簡単に保険診断ができる「ほけチョイス」の活用がおすすめです。
自分に必要な保障を見極め、納得のいく保険選びをするための第一歩として、専門スタッフによるサポート付きの診断サービスを活用すれば、保険への不安や疑問も解消できるはずです。